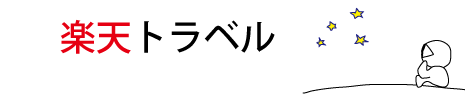|
|
||
|---|---|---|
|
アラブで最も貧しい国(2002年にイエメンを訪れたときの旅行記です)
集落に着くと、先ず宿に案内された。3、4階建ての飾り気の少ない武骨でまっ四角な日干し煉瓦の建物だった。窓は小さく頑丈そうな木製の雨戸が取り付けられている。建物の中に入って滑りやすい薄暗い階段を上ると、黄、赤、緑、青の色の光が射し込んでいた。この武骨に見えた家にも、色ガラスの窓が使われていた。案内された部屋には、赤いふかっとした絨毯と堅い肘掛クッションが置かれていた。おやじはどかっと座ってその部屋から建物の奥の方に向かって何やら叫ぶと、お茶がポットに入って出てきた。おやじは自分の家を宿として提供しているらしかった。
開きかけの部屋のドアからは小さいけれどくりくりした方っぽの目が覗いていた。そのくりくりの目の小さな女の子は興味津々といった表情でこちらをのぞいていた。とても入りたそうにしていたが、決して入ろうとはしなかった。どうやらここは男たちの部屋ということだろう。ドアが開いているときに、ドアの入り口に女の人の声がしたのでそちらを見ると、そこには黒いチャドルを着たでっぷりしたおばちゃんが立っていた。ここでは家の中でもチャドルを着るようだ。ただ、ベールはしていなかったためか、目が合うとぎょっとした顔をしていた。思春期云々に関わらず、女たちは顔を見られることを嫌がるのかもしれない。
晩飯もこの部屋で喰った。出てきたのは鶏とジャガイモのシチューや、スパイスの効いた黄色いピラフ、羊の炒め物などなど。意外なことに、こんな山のてっぺんの食材が乏しそうなところで、こんなしっかりと味付けのされた家庭料理が喰えるのかと思うぐらいうまかった。
|
||
| |
||
|
(C) Tabinchu Terada |
||