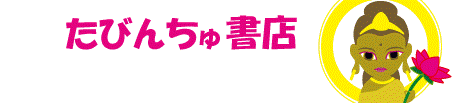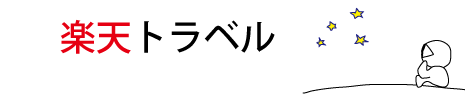|
|
||
|---|---|---|
|
西蔵法師 −原作 河口慧海のチベット旅行記−
解説さて、私たちがラサで飲んだこのジンタン。慧海が紹介していた奇々妙々の薬と恐ろしい符合を見せます。私たちがラサで飲んだ丸薬が法王というような高等なるラマ達の大便を小便で捏(こ)ねた「本物の」ツァ・チェン・ノルプー(宝玉)でなかったことを祈るばかりです。 まあ私のチベットの旅の思い出話はこれくらいにして、河口慧海のチベット旅行記の解説をしてみたいと思います。慧海は日本で釈興然師からインドのセイロン(現在のスリランカ)に行って小乗仏教を学ぶよう勧められます。それでも慧海は、 「たといどれだけお金を戴きどういう結構な目に遇いましたところが、私が日本国家に必要なりと信ずる大乗教の主義を棄ててあなたの信ずる小乗教に従うことは出来ません。今日まで教えを受けたのは有難うございますけれどもそれはただ語学上の教えを受けただけでその主義に至っては始めから教えを受けたのでないからこれは全くお断りを致します」 と断ってしまいます。 また慧海がダライ・ラマ一三世に対して認(したた)めた上書の大意は、 「まずチベット風に法王に対し敬意を表する言葉をまず書き列(つら)ね、それからこの雪をもって清められたる美しき美の主人に対し、私は世界の人民の精神的苦痛を救うために、真実仏教の発揚を希望してこの国へ来たのである。今世界に仏教の行われて居る国は沢山あるけれども大抵小乗仏教である。 大乗仏教の行われて居るシナ、朝鮮およびネパールのごときは全く見るに足らない。ただその大乗教の真面目を維持し世界における仏教の粋として今日に現存して居るものは、我が日本仏教とチベットの仏教のみである。そうしてこの尊いところの純粋仏教の真理の種を世界各国に蒔(ま)かなければならん時は確かに来(きた)って居る。世界万国の人々は肉慾的の娯楽に飽きて、精神的の最大自由を求めようということに熱中して居る。この時に当って真実の仏教をもってその欠乏を満たすに非(あら)ずんば、今日大乗仏教国の我々の義務が立たない。面目が立たない。それ故に果たしてチベット仏教が、真実我が日本国家の仏教と一致して居るや否(いな)やを取調べるために私はこの国へ来たのである。 幸いにしてチベットの新教派の仏教は確かに我が国の正統派の真言宗と一致して居る。その教祖(龍樹菩薩)もまた一致して居る。かくもよい教えを持って居る両国の仏教徒は、互いに合同して世界に真実仏教の普及を謀(はか)らなければならん。これ私が千辛(しん)万(ばん)を忍び、雪また雪を踰(こ)え川また川を渡ってこの国に出て来た所以(ゆえん)である。その真実の精神は仏(ぶつ)陀(だ)も感(かん)応(のう)在(ましま)して、この誰もが入り難い厳重なる鎖国内に到達して、今日まで仏教を修行することが出来たのである。この国の仏教守護の神々も我が誠心の願望を納受在(ましま)して、ここに止まって仏道を修行することを許されて居るのである。 しからばかくも仏陀と仏教守護の神々が保護されたる私に法王殿下の保護を与えられて、共に仏教の光輝を世界に輝かさんことを力(つと)むるは、実に仏教徒たる者の最大義務にあらずや。私は大いにこの事を希望して已(や)まんものであると説き、それからセイロンのダンマパーラ居(こ)士(じ)から、インドのブッダガヤーの金剛道場の菩提樹下において、釈迦如来の舎利と銀製の舎利塔とを法王に献上してくれろといって頼まれて来ましたからこれを差し上げます、という文句を入れて帰結を付けたのです。」 と原作のチベット旅行記の中で書かれています。 |
||
| |
||
|
(C) Tabinchu Terada |
||