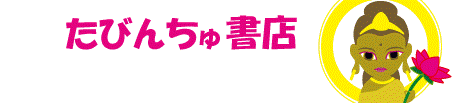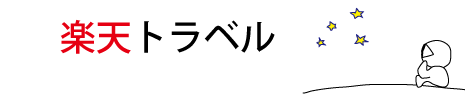|
|
||
|---|---|---|
|
西蔵法師 −原作 河口慧海のチベット旅行記−
解説一方、玄奘三蔵が孫悟空らを連れてインドへ経典を取りに行った物語、西遊記にもこんなことが書かれています。 「そこな和尚の説かれるは、おしいかな小乗仏教じゃ。小乗はあさくて俗でとるにたらぬ。なにゆえ大乗を説かれぬか。」(西遊記〈上〉 本書では主に慧海の旅程を抜粋して紹介しましたので、ここでは慧海がチベットに求めた大乗仏教原典について書いてみたいと思います。その前に小乗仏教と大乗仏教との違いの説明をご紹介しましょう。 広辞苑によれば 大乗仏教とは「紀元前後頃からインドに起った改革派の仏教。従来の部派仏教が出家者中心・自利中心であったのを小乗仏教として批判し、それに対し、自分たちを菩薩と呼び利他中心の立場をとった。東アジアやチベットなどの北伝仏教はいずれも大乗仏教の流れを受けている。」 小乗仏教とは「衆生済度を忘れて自己の解脱だけを求める声聞や縁覚の立場を、大乗の立場から批判的に名づけたもの。」 とされています。 また、長尾雅人さんは「世界の名著2大乗仏典」(中央公論社)の中で、 「ところで、仏教の修行者のタイプは、その学ぶ態度によって、声聞と独覚(縁覚)の二種(二乗)にまずわけられる。この両者は一括して小乗教徒とよばれ、大乗の菩薩bodhisattvaという修行者に対立せしめられる。その中で、「声聞」とは、説法を聞く者という意味で、仏陀の直接の弟子をさす。・・・しかし、この場合の声聞は、聞くことに拘泥し、教えを墨守し、教えが「空」であることを知らない小乗の徒である。 次の「独覚」は、他に教えられることなく、自力でもって真理を悟るものであり、また利己的であるゆえに、その真理を他に向かって説こうともしない。」 「何が大乗、何が小乗かという、大小乗の区別の基準はさまざまに説かれる。たとえば、大乗は利他の精神からなり、在家主義、空観主義であるなどと。」 「菩薩bodhisattvaは、一般に「悟りを求める衆生」の意味である。小乗では悟りを開く前(幾多の前生を含んで)のゴータマ・ブッダ(お釈迦さま)をさすことにかぎられたが、大乗ではゴータマに限定せず、悟りを求める求道者として一般化された。したがってある意味では、あらゆる衆生が菩薩である。彼らはすべて、やがては悟りを開き成仏すべきものであるから。しかし、すべての衆生が救われないかぎり、自分もまた救われないであろう、という誓願が菩薩にはある。このような菩薩の理想のタイプが擬人化され象徴化されて、観世音菩薩、弥勒菩薩、文殊菩薩などの諸菩薩が案出された。」 と、書かれています。 |
||
| |
||
|
(C) Tabinchu Terada |
||