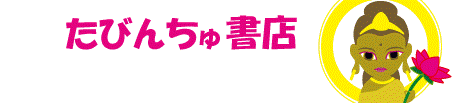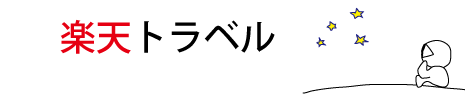|
|
||
|---|---|---|
|
西蔵法師 −原作 河口慧海のチベット旅行記−
解説この般若心経の現代語訳もいまでは岩波文庫の「般若心経・金剛般若経 、岩波文庫 「仏典が日本のことばで伝えられていないということは、日本文化にとって致命的な問題である。明治以降は漢文の書き下しも刊行されたが、それは必ずしも日本のことばとは言い難い。仏典を現代語に訳し刊行するということは、いま諸方面から要請されている。」 と書かれています。ここで名前があがった長尾雅人さん、中村元さん、早島鏡正さん、紀野一義さんをはじめろいろな方々が仏典をサンスクリット原典などを参考にしながら現代語に翻訳されています。これは慧海の 「どうか平易にして読み易い仏教の経(きよう)文(もん)を社会に供給したい」 「原書に依(よ)って」「素人(しろうと)にも解り易い経文を拵(こしら)えたい」(原作より) という志が受け継がれた結果と言っていいのではないでしょうか。 あらためて、本書では主に慧海の旅程を抜粋して紹介しました。それは西遊記の三蔵法師、玄奘三蔵の名を多くの日本人が知っているのに、西蔵旅行記の西蔵法師、河口慧海の名を知っている日本人があまりに少ないのを残念に思い、百五十四回にも及ぶ原作のチベット旅行記を短くして少しでも多くの人の目に触れることを期待したからです。割愛した部分にまだまだ面白いところや重要なところが沢山あります。 たとえば原作の「第百七回 チベットとロシア」で慧海が語る当時のチベットと他国との関係は、後に私たちが知る世界史での勢力図を彼の皮膚感覚を通じて伝えてくれているように思えますし、現在の中国とチベットとの関係の複雑さも垣間見れる気がします。 「シナの無勢力 その上まだチベットをしてロシアに頼るの心を深からしめた所以(ゆえん)は、日清戦争以来シナの勢力が日々に衰えて、チベットの方へは全く及ばぬようになったからでもある。これまではチベットの法王が少し変った事をやるというと、シナ政府からじきに異議を唱えられ、あるいはそのシナ皇帝の命令の下に罰せらるるという虞(おそれ)があった。全く君と臣の関係程になって居ったです。ところがこの頃は余程変った事をやっても手を着けることが出来ない。すなわちテンゲーリンを滅ぼし、そしてテーモ・リンボチェを亡き者にするというようなああいう大騒動を起しても、シナはそれに対して一定の責を問うことも出来ない。 また問うてみたところが到底駄目なんで、それが気に喰(く)わなければお前の下に付かないとこういわれた時分には、チベットにあるシナの兵隊はチベット国人に殺され、チベット在留のシナ人ももちろんチベット人に殺されてしまうだけの話で、とても今日の有(あり)様(さま)ではシナ政府がチベット内地に踏み込んで征服するというような事は出来ない。その事はチベット人はもうよく知って居る。ですから法王それ自身の考えとしてもシナ政府には拠(よ)ることが出来ず、また英国の主義というものはうまく人を懐(なず)けてその国を奪うのが主義であると聞いて居るので、もとよりこれと親しむことが出来ない。で、その一番英国に反対して居るロシアと親しく交際するということは、外交上実に無上の策であるというような具合に考えたと察するです。 かの考え深い法王が、訳もなくかの綺麗なビショップの法衣をくれたからというて貰うような人でありませんから、きっとそういう考えを起して貰ったものと私は信じて居る。そのビショップの法衣を貰うた返礼として、法王はズーニェル・チェンモ(侍従長)とその従者三名ばかりを使節とし、明治三十三年の十二月ラサより北の方へ路を取り、ツァンニー・ケンボの国を経(へ)て鉄道に乗り、幾月かを経てロシアの首府に達し、そしてチベットの珍しい物をロシア皇帝に差し上げて充分に返礼の敬意を表したという。・・・」 また原作の第九十二回 法王の選定に続く第九十三回 子供の選択では 「・・・だから化身の信ずるに足らんということはもう分り切って居る。昔の事はいざ知らず今の化身というのは本当の化身でなくって 賄賂の化身 であると私は言った事がある。それでもその子供に自信力をつけてよく教育するものですから、どうも化身と称するラマは十人の内でまず八人までは出来の好い方です。二人位は屑(くず)もあります。その教育の方法は教師も付添人もその化身とされし子供に対して鄭(てい)重(ちよう)に敬語を用います。喩(たと)えばその化身の子供につまらないことがあっても無(む)下(げ)に叱るということをしないで、あなたは化身であるのにさようなことを遊ばしてどう致しますかというて反省させる位のものであります……。だから私は少し考えた事がある。どうも子供を無闇に馬鹿だの頓(とん)馬(ま)だのと罵り、あるいはその記憶力の足らぬ事判断力の足らぬ事をば無(む)碍(げ)に卑(いや)しめてその自信力を奪うという教育法は、確かにその子供の発達を妨害する教育法だと思います。」 と語っており、教育方法による子供の発達の可能性にも考えさせられるところがありました。 |
||
| |
||
|
(C) Tabinchu Terada |
||